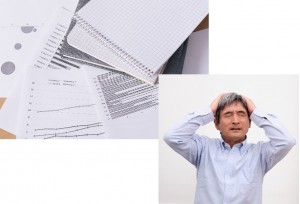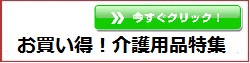誕生の背景
アンシアーノは、以下の課題や要望を基に誕生したサービスです。
記録作成の課題
記録に費やす時間が増えて直接サービスの時間が減ってしまった。
・記録作成の負担
・活用面での悩み
・質的向上の必要性
・記録の転記が多すぎる。
・職員により、記録品質に差がありすぎる。
・蓄積された膨大な記録を有効活用できていない。
・欲しいときに必要な情報が探せない。
職員の皆様は、サービス利用者のその日の状態、食事量、バイタル記録などを「通所介護連絡帳」に記録しご家族様へご連絡を行っておられます。
しかしながらご多忙の最中、空いた時間を見つけてそれぞれのご利用者様への記録を個別に、記憶をたどりながら文章を構成していくことは大変な業務と考えられます。
また、限られた時間の中での作業となるため、全ての状況を記述することができず、職員の皆様の「思い」を正確に伝達することは難しく、フラストレーションがたまることもあるかと存じます。
ある事業者様は、パソコンにそれぞれの記録を記述し、プリントアウトした紙を連絡帳に綴り、ご家族様と共有なされようとされておりましたが、職員同士、書く時間が重なりパソコン待ちが発生したため、手書きに戻されたとのことでした。
また、サービス利用者と同居しているご家族は、「通所介護連絡帳」を読むことができますが、遠方にお住まいのご家族の方は、同居しているご家族に近況を尋ねることしかできませんでした。
社会環境の変化
2014年3月25日付 産経新聞に以下の記事が掲載されました。
特別養護老人ホームへの入所を希望しながら入れない待機者が、昨年10月時点で全国で52万2000人に上ることが25日、厚生労働省のまとめで分かった。平成21年の前回調査(42万1000人)より約10万人増えた。
同省によると、全国の特養ホーム7865施設で受け入れ可能な高齢者は現在51万6000人で、すでに満床。それを上回る人数が“順番待ち”をしていることになる。まとめによると、待機者52万2000人のうち、在宅介護を行っている人は約半数に当たる25万8000人。残りは老健施設や病院からの転入を希望していた。要介護度別では「3」以上が66%、より軽度な「2」以下が34%だった。
入所の必要性が高い要介護「4」「5」で、在宅のまま待機しているのは16・5%に当たる8万6000人(前回調査時6万7000人)だった。
高齢化による入所希望者の増加に施設整備が追いついていない状況で、政府は27年度から、特養入所者を原則として要介護「3」以上に限定する方針だ。同省では「必要な施設整備を急ぐ一方、在宅サービスの拡充などで対応していきたい」としている。
2014年3月25日 産経新聞
要介護者の需要が施設の供給を大きく上回っています。
「特養」や「老健」(のショートスティ)に入所できない要介護者やその家族は、通所介護(デイサービス)のお泊りデイを利用せざるを得なくなります。
ますます高まる記録の重要性
介護保険法に基づく厚生省令第39号「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」、厚生省令第46号「特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準」にて、
例えば東京都の「指定介護老人福祉施設特別養護老人ホーム(老人福祉施設)指導検査基準」のように、全般的な記録の整備状況を検査するとともに、法令の趣旨からして実施の遵守とともに、それを裏付ける記録として、個々にも適切に記録が残されていることの確認がなされています。
現在、日中のデイサービスは、介護保険に基づき提供されるサービスのため、職員の基準や設備での基準が定められていますが、お泊りデイは介護保険外で提供されるサービスなので、全国一律の法的基準がありませんが、東京都や大阪府では独自の基準を設けており、前述のような背景から法的整備も検討されています。